公開中の戯曲
劇団青い薔薇・劇団由の戯曲を著作権フリーで公開しております。
打ち込みや校正作業が終わり次第、戯曲を追加していきます。
表紙画像もしくはPDFアイコンをクリックして、ご自由にご覧ください。

あの白い部屋AB
この作品は、江口が休業中にずっと書き続けて居たモノで在る。
ソノ江口を支え続けたこの作品は、きっと世の人
も救うで在ろうと信じて居る。
すでにノートで200冊を超えるこの作品は、
既存の作品で言うと「ROOM in ハート」に、類似するかもしれない。
しかし、もっとハードで、問題作だ。
今も書き続けるコノ作品の冒頭部分を劇曲にしたモノだ。
それでも、普通よりも長い、コノ劇曲を上演する事は難しそうだ。
ソレでも、皆さんに、どうしてもお目に掛けたいと
あえて、劇曲で提示する。残りは小説で?と考えて居るが、
それは又の機会に。
長くは在るが、ソノ『白い部屋』を出る劇的部分まで、収められ、
中々、いい作品に仕上がって居る筈だ。
タブーの世界を描いて追求する、この作品が
世の人に受け入れられ、弱者や弱者のまわりの人々へと
バイブルや指南書に成ればと願って居る。
未上演作品
(2025年7月27日掲載)
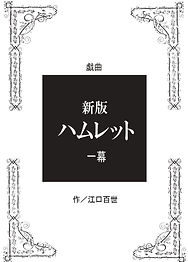
新版ハムレット
新版ハムレットは 劇団由の旗揚げ公演だ。
志は高いがまだまだ実態の伴わぬ状況で在った。
何とか、シェークスピアの力を借り、 シェークスピアを超えてやろうと、豪慢に考えて居た。
ソレが成功したかは観客に委ねられるが、その一端は、この戯曲に処って垣間見れるだろう。
4人で9人程を演じる。 一人を二人で演じる。等、
言葉では 解りにくい所も在るのだが、
ソレを上演し、 目の前で観せると意外に解りやすい筈だ。
前筆の操作に処る何重もの深みも読み取ることが出来る。かもしれない。
ハムレット作品の面白さ、名台詞を残し、
削ぎに削ぎ、 新解釈を大胆に加えた。この作品は劇団由の旗揚げに相応しい作品に成ったと自負している。そして、ワクワク、ドキドキ出来る作品だったと聞く。
それが 読者に届けば幸いです。
1980年 上演作品
(2025年1月15日掲載)
「遠きは花の香 二幕十場」
この作品は劇団青い薔薇の最後の公演となった。
しかし"さよなら公演"ではない。
昭和初期の東京が舞台で、雰囲気としては昔の新劇のような作品。クラシカルな空気に充ちている。
同じ場面を3回も出すところは大胆な構成だ。
基本的には、少女の成長物語では在るものの、女性の自立の問題。
戦争が引き起こす夫婦の愛憎。
そこから派生する親子の問題。姉妹の事。
又、当時の美術界の空気から発生する自滅と死。
それに伴う心中事件。
又、義兄を愛してしまう主人公等々問題が散りばめられている。
場面は主に二つ。
一つは、主人公の家、安藤家(リビングと庭)と、もう一つは、当時の芸術家?達が集う"カフェシャノワール"だ。
安藤家には、母(綾)、姉(園子)、ばあや、ばあやの孫(里美)、そして姉の婚約者(向井修一)が配され、シャノワールには、画家(涼)、踊り子(チェリー)、女優(夏子)、修一、そして、ママ、従業員に久美とまり子。若き書生達が配され、十二分に楽しめる作品に成っている。
1999年上演作品
(2022年10月17日掲載)
「幻奏交響曲」
コノ作品は、当時"自信作"とか江口は言っている。
今となっては恥ずかしいが、主な出演者は五名。
メインはモノローグ的台詞が続き、回想では会話劇的。屋敷内とソノ庭がメインで、屋敷内を黒バックで庭を木立で表現して居る。逆に3回登場する回想シーンでは、大掛かりな装置。
大正、昭和初期を感じさせる〈駅〉〈楽屋〉〈遊郭〉の回想。
ソレに比べ普遍的に処理されるメインのストーリー。
登場しない夫が死ぬ日 妻 草子は何を語るのか?
その娘〈海(カイ)〉は何故男として生きようとするのか?
木(モク)と呼ばれる青年(少年?)は何者なのか?
木(モク)の愛する人形の存在とは?母、千鳥とは?
草子の回想から海(カイ)の出生の秘密が浮かび、幸福屋の過去から、ストリッパーのマリーが現在に登場し、その存在と出現が他の出演者の心情、現在を動かす。
ソノ五人が絡み合って描かれる作品。
コノ作品の木(モク)は"真昼の宵"でメインパーソナリティで登場。又、その後"幸わせの庭""水の人"と同類?の作品が描かれ続ける。ソレ等の根源的作品。
1984年上演作品
(2022年9月7日掲載)
「幸わせの庭」
"幸せ"を"幸わせ"と表記している。
幸せというモノを根底から問うて居る?
この作品は三島由紀夫氏のサド公爵夫人をヒントに描かれている。日本に置き換え、似て非なる作品に成っている。劇団由では珍しい会話劇。時間も前後しないし、心象風景も無い。同じ人物を二人が演じたりしないし、一人が何役もやったりもせず、歌も踊りも無い。
この家、佐渡島愛造の家に住む、愛人、元妻、元妻の妹、居候、元妻の娘、元愛人の娘。今から、妻に成ろうとする若い女。その女の登場から物語は始まります。複雑な人間関係と人間模様。ココの住人が何故ココに住まうのか?佐渡島愛造という男に何を求めたのか。謎は会話の中で解かれて行きます。
一幕目は結婚式の一日。二幕目は葬式後の数時間を描きます。
劇団由では珍しいストレートプレイをお楽しみ下さい。
1991年上演作品
(2022年2月27日掲載)
「夜明けの人間美術館」
設定が面白い。絵の中の世界と外の世界。
ドラキュラ(血を吸う生き続ける者)と人間。
双子の兄弟〈見た目はいい兄と見た目は醜いが心の良い弟〉
又、母と娘。〈ドラキュラ姉妹?〉
父と子。〈マイケルジャクソン?とキリンのマハリ〉
女の子たちの夢。〈捕らわれた花嫁候補?〉等々、ソノ総てを絡めて、謎の美術館で起こる物語。
ドラキュラの映画も多々在り、マンガも然り、しかし、ソノどれも一線を画する作品。
修学旅行生と思われる男子学生がワラワラと登場し、美術館を見学する始まり。
変わったガイド〈ウサギ〉が説明する一枚の絵。美術館のソノ絵の中の世界〈ドラキュラの館?〉。
ソコは、はたして、エデンの園〈世界〉なのか?怪しく怖しい?誘惑の虚構現実の世界。
1989年上演作品。
(2021年4月15日掲載)
「青空のむこう側 ─ 画家ユトリロの哀しみをのせて ─」
この作品は、小説よりも奇なる。画家ユトリロの人生を知り描かれている。
ユトリロと魅惑的な母。そして親友との関係性。幼くして、アルコール中毒に成らざるを得なかった人生。
ソレを描いている。しかし、作者は、天国や現代を絡め、在る意味解りにくくしている?
時はユトリロの生きた時代と、上演時の現代。ノストラダムスが地球壊滅を唱えた1999年まで9年の年。
また、天国では、ソノ1999年が過ぎたと言っている。あまりにも悲惨だからこその美しい舞台。
段々に山に成った舞台に、白い雲の浮かぶ子供部屋のような"青空"。心模様を現わす"抽象画"。深い闇を表す"黒"のパネルが舞台を彩り、象徴的にその展開を助ける。
ソノ世界の中で何を伝えるのか?
舞台らしい、舞台とも言える。
1990年上演作品
(2021年3月25日掲載)
「FATAL -フェータル - ’94年度版新版『ハムレット』」
フェータルは、実験公演と銘打っている。
もちろん、ハムレットの脚色なのだが、あまりにもの変更に、
ハムレットと謳うには、おこがましい程の変更ぶりで「FATAL」としている。フェータルには、"運命的""宿命的""致命的"等の意味が在る。ハムレットという作品の本質をどう観たのかが鍵。既存のハムレットを観ると、登場人物の多さに困惑し、又、"何故こんなに人が死ぬのだろう?"と疑問が湧く。なので、少し、生かしてみました。もちろん死す人も居ます。そして初演の新版ハムレット同様、男優2人、女優2人で、登場人物を絞って、コノ"フェータル"は演じられる。どう変更し、どう踏襲したかも見モノです。
「尼寺へ行け、尼寺へ。」「死すべきか?生きるべきか?」等の有名な台詞たちの扱い、登場のさせ方もお楽しみいただきたい。
ハムレットという芝居をよくご存知の方にも、ハムレットという名を知っていても、ほとんど内容は知らぬ方にも、お楽しみいただけるはず。
ハムレットを〈学生〉とした、コノ芝居、とくとご覧あれ。
最後に、本家のシェークスピア作「ハムレット」を比較の為、お読みいただくのも一興。
1994年上演作品(2020年11月22日掲載)
「この時間を抱きしめて」
この作品は、吉本ばななさんの「キッチン」という作品を読み、コノ作品と"似て非成るモノ"を創りたいと想った。そして出来上がったのがコノ作品である。
奇妙な不思議の国の住人成る人々も登場する。
他には、詐欺師とか、ヤクザ?とか、ダッチワイフ?とか、ゲイらしき人とか、登場し、"たかし"君の父母の関係を見せながら、出会い系やら愛や友を失った人々の優しい関係を見せる。
コノ作品が優しい仕上がりに成って居るのは、吉本ばなな氏の「キッチン」が根底に在ったからであろうと思う。たかし少年とたかし青年が、交錯して登場するあたり、由らしいというか、江口作品らしい作品でも在る。
1988年上演作品
(2021年8月7日掲載)
「ROOM in ハート 天国へ行きたかった猫たち PartⅡ」
1997年上演
この作品は"天国へ行きたかった猫たちPartⅡ"と銘打たれている。
確かに猫耳を付けた人たちが出て来る。しかし、Ⅰとは違って、実在の有名人は出て来ず、歌も踊りもなく、つまりミュージカルではない。どちらかと言うとストレートプレイ・モノローグの多い芝居だ。
題名に在る通り、部屋の中で物語は展開・転回する。オタクや援助交際の女子高生など時代背景も捉えつつ、不思議な出合系?の部屋?人々が壁向きに座る部屋。出演者(登場者)が言った通りに変わる部屋。等。
ソノ世界は複数の部屋から構成されている。知らない人々が出会い、普通なら会う事も話す事もない人が出会い、話し合う。意外に深い話しまでしてしまう部屋。面白い空間です。
若い子等が由に入って来て、子等に"より良い世界を"と描かれた作品です。プロデュース公演で沢山の日替りゲストにも出て頂き、アクセントにも力にも成り、ソノ工夫も在ります。猫(人間)たちのリアルな不思議世界ご堪能下さい。(2021年7月8日修正版掲載)
「青空への階段」
未来の話である。SFというには、クラシカルな趣。
日本が壊滅的に崩壊。東京も完全崩壊していて、各地区毎にようやくドームによって守られ、閉じ込められて居る。その東京にあるサロンBUBUSが舞台。
ドームの外は人の生きられる空間ではなくなっている。それでもコノ作品のコンセプトは明るく楽しくだ。しかし、劇団由(江口)なので、重く暗いかもしれない。
だからこそ?歌あり、踊りあり、漫才まである。
人は人類が死に絶えるような不幸に直面した時、そんな、どん底、苦しさの中で、ソノ心持ちから逃げ、遊ぶかもしれない。
そうしても、人は生き続けようとする。そして、ソノ後人は、"生きる"を考えるだろう。
話のベースの‘かぐや姫’?。イルカをキーワードに、官制を敷かれ脱出不能な世の中で、姫の願いに、遊び呆けて居た若者三人+αが動き出す。
コロナ禍の今、タイムリーな作品かもしれない。
1998年上演作品
(2021年5月8日掲載)
「約束の時間 1+1+1+=4」
実験公演というスタンスで、出演者は女(娘)3人のみ(最後に男が登場するが)演りやすい芝居だ。
由の本公演では、装置、衣裳、音効、照明等、総てを駆使して全力で演者をバックアップする事にしているが、コノ公演はソレ等に頼らず、スローモーションもストップモーションも無い、会話劇だ。停留所というワンシチュエーション。ソレも外と中、戸口さえ解り、座る場所が在ればいい。
真面目な図書館に勤める加奈子。
AV娘に成ったユカリ。
少し頭と心がおかしいキエ。
ソノ3人が停留所で出会い知らぬ人3人が、会話の中で同級生と知る。ソノ想い出の中へ戻る小学生時代が描かれ、後は恋する乙女の現在が描かれる。ソレゾレが待ち合せした男を待つ時間。
それが〈約束の時間〉なのだ。3人は幸せ行きのバスを待つ。
1993年上演作品
(2021年9月20日掲載)
「真昼の宵」
1986年上演作品
コノお話しは、〈顛末を言うのは得策では無いが、〉少年の皮を覆ったまま、生きる老人の話しだ。
大衆の中の個人は周りが騒がしければ騒がしい程、孤独だったりする。ソノ衆と個の対比。又、彼に影響を与えた女たちの同一性と異質性。ソノ女たちも彼を救いはしない。
そんな、コノ芝居を気に入ったと、だいぶ昔になるが高校生が上演したと聞く。
ドコが気に入ったのだろう。
老人の分身、子供時代の主人公も寄り添い、叱咤する。女たちは皆美しく、男たちもチャーミング。まあ、舞台の上くらい幻想を持ちましょう。由の特異性、美しさ、ソノ夢世界。
衆を芝居小屋を中心に描いたトコロも面白くしているかもしれない。
又、映像と生(舞台)をミックスした実験的、先鋭的作品でも在った。
(2021年9月20日掲載)
「天国へ行きたかった"猫"たち」
この作品は劇団四季の"キャッツ"に、イマジネーションを喚起された事は間違い無い。しかし、猫の姿を借りた人間の話だ。何しろ、彼等は総タイツでも猫メイクでも無く、人間の姿に猫耳と尻尾だけを付けて居る。ミュージカル仕立てにした部分もあるが、核の部分はストレートプレイだ。
"出口なし"や"カッコーの巣をこえて"等のリスペクトさえ利用?して、この不思議な世界を構築しようとする。劇団由の力技が見える。
又、"沖雅也""川俣軍司"という当時の実在有名人を配して観客の共通イメージを喚起して、物語を転回して行くという技を使った問題?作でもある。
人間では無く"猫だから"と逃げ道をつくったコノ作品は特異だがファンも多い。
多分シリアスに見える底に温かさが流れて居るトコロに拠るかもしれない。
1984年2月上演。
(2021年9月4日掲載)
「夢の音」
この作品は珍しく、原作がある。吉村昭氏の作品「煉瓦塀」という短篇である。
この吉村作品には、エラク感動してしまった。
この作品の〝子供〟〝馬〟という二つの点、その他、場所が短い時間にめまぐるしく変わる点等々、芝居にするには、むずかしい。しかし、芝居には芝居にする、〝絵〟があるわけで原作通りではない。けれど、原作をほとんど変えていない場面もある。それだけ、私が良いと思ったわけで、その良いと思ったものを伝えるというかたちでの初めての芝居づくり。その良さが、美しく、美しく、シビアに、私というフィルターをとおして、より、より伝えられたらと思っている。
※この紹介文は、上演当時の〝解説にかえて〟の抜粋です。戯曲の終りに全文を掲載します。ご参照ください。
又、上演時の吉村昭氏のお手紙内容も載せる予定です。ご参照下さい。
(2020年7月20日掲載)
「無題─ある女の生と死・疑問の跡─」
この作品は江口君子の追悼公演である。
"江口君子"とは江口百世の母で在る。ソノ母は劇団のスポンサーでも有り、ファンでも在った。
そして、もちろん、江口百世を産み育てた人でも有る。(色々な意味で)
さて、期間、時間の無い中で、創られた作品だが、一つの作品として、ソコソコ仕上がっていて、驚く。
母の想いを 四人の女性に振り分け、ソノ多面的な 彼女?
また推論を表現する等、随所に由らしさ?江口作品らしさも覗く。
又、出演者が本人として出て居るのも珍しく、本人から演者へ、演者から本人へと推移するのも面白い。
ソノ今の時間と彼女(母君子)が生きていた時間とを行き来するのも、由らしい、由らしさとも言える。
最後の部分は江口本人が言っていた通り蛇足に想えるが、ソレは見た人、読む人に委ねる。
(2020年9月24日掲載)
「夢を想う日々~2008年もうすぐ卒業~(三条公演)」
新潟県三条市で、悩める青年たちを救おうと企画されたこのプロジェクトに、呼ばれて始まった"芝居(演技)をするプロジェクト。"私は芝居をする以上、公演を打たなければ駄目だと駄々をこね、最終的に発声から始まった当初の練習だけでなく、公演用の練習を重ね、装置造り等々まで、まったくの素人?もしかして、そうやりたくない?青年や三条の人々を捲き込んで公演を打った。当時の題名は"夢想"。
きっと救われた青年も居たと信じたい。という作品なので、江口作品ぽいモノで在りながら、解りやすく、やり易く出来て居る。悩める青年たちが卒業を前に色々考え、仲間と共に、一筋の光を見つけて行く。キャラクター配置も良い。とにかく、学生さんや若い人たちが、使用しやすい、やりやすい作品に出来て居る。ぜひ、読んでみて下さい。
最後に、当時、ご協力いただいた三条の人々。又、作品に出演して下さった人たち、モノつくりをして下さった方々。ソレを許して下さった三条市の方々ありがとうございました。
2008年上演作品(2020年9月24日掲載)
「カルペ・ディエム企画 祈りの中のプレイ
Play in Pray」
高橋郁子というプロデューサーが付いて初めてプロデューサー付きの芝居創りだった。
だから、コレは正確には由の公演では無い。爆男倶楽部の男優陣や高橋さんの関係の女優さんも出てくれた。
高橋郁子曰く「エッチな芝居がやりたいんだよね。」と要求された。いくらHな私でも正面切ってソウ言われると、躊躇する。
ソレで少年が青年に成る時のソレばかり考える時代を少年の妄想を具現化するパソコン内の世界という形で、美しく、幻想的に仕上げた。
1999年上演作品
(2020年5月8日掲載)
「水の人 - RENJOU - 」
1992年上演作品
大正、昭和の古き、良き時代の香りのする文学や映画等を意識した作品であり、
また、ビスコンティの母への愛情にも似ている。静かな作品を創りたいと始まった作品。
基本を広い湖のほとりを舞台にしていて、ソノ現在、過去、幻映と変わっても、ソコは変わらない。
90才に成った佐田仙太郎を主人公に、真面目に生きようとしたソノ人の人生が恋情と、悔いを中心に描かれる。ソノ子供時代から、大学時代、そして現在。想い出と悔いの中に沁み込んで居る仙太郎老人の前に、亡くなった妻と、若い女性、小町隣子が現れて、物語は展開して行く。想いを遂げなかった相手、雪乃との物語。親友、龍との関係。大きな存在だった月子おばさん等々、人員配置も良いバランスだ。
(2019年12月28日掲載)
「青い庭 多くの優しき冒険者へ」
2019年の今、AIやロボットが身近に成って来て、
今後、社会、世界がどうなるのかと少しの心配を持って考えられるように成った。
しかし、青い庭はソノロボットが街に溢れた世界。
それでも、少年は夢を見。自分の可能性を迷いながらも信じ走り出る。
迷い出た先にはマザーと呼ばれる女とソコへ集まった男たちが疑似家族をつくっている。
ソレゾレの想い。何かを求め、夢を迷う。その一つの夢を形にしたかの様な人造人間の存在。
男たちが本当に求めているモノとは?
自分にとって、存在するモノとは?と問う1993年上演作品。
(2019年12月17日掲載)
「夢・見果てぬはて -あるスターの場合-」
1987年上演作品 私(江口)は、ジャニーズアイドルの歴代スターたちから、ソノ人を信頼する力、自己プロデュースする力、輝きをファンに届ける力等々リスペクトしていて、いつも深い関心を持って見て来た。
その最初が田原俊彦くんで(私にとってだが)コノ作品では、そのリスペクトを込めて、田川俊介として描かれる。だからと言って、トシちゃんの物語では、もちろんない。あくまでフィクションで在る。
ジャニー喜多川氏が亡くなった。その為歴代のスターたちの姿が次々に流れた。ソノスター像に似た(あくまで似た)人物が、自分を隠し、ネジ曲げ、生きて行く。その己との葛藤。自分を取り囲むモノとの葛藤。そして精神崩壊。自分を利用して、駆け上がる若きアイドルスターがそこに拍車をかける。信頼するマネジャーと担当記者が絡んで、ソノ夢の見果てぬ先を提示する。ソレは、ほぼ真白な舞台で描かれる。
(2019年9月9日掲載)
「さあ、たいへん 四姉妹が結婚だ。」
演って楽しい、観て楽しい。コメディ作品。
4姉妹は性格も違い、状況も違い、考え方も違う。
結婚、恋愛、結婚相手との関係もソレゾレ。
キャラクターを良く理解して、誰かに当てはめて読むコトをお勧めします。
練習用台本としても、
役者のキャラクターづくり、会話のリズムやテンポの練習としても楽しめます。
由としては珍しい"軽い""楽しい""笑い"のある有る在る系戯曲。ブライダルフェアでの上演作品。
(2019年8月19日 掲載)
「パープル・ストーム」
江口作品の中では珍しいSF作品。当初、江口の頭の中では"ロマンチック活劇"と副題を付けようとしたとか。(SFが珍しいのでは無く活劇の方が?)
核戦争とか原発とか今、話題に成るが、核戦争とか核のゴミ等を意識した1985年上演作品。
深刻さを深刻なままでは捉えず、汚染地域で強かに純粋に生きようとする人達を西部劇タッチ、活戯タッチで描く。汚染から産れたニュータイプと呼ばれる人間や、ゴミ人間?ネコ人間?等不思議&楽しいキャラクターも登場。SFならではのお楽しみをちりばめ、ショーの"スター"と呼ばれるダンサーが戦いでも強いという美女?を配したり、演る側も観る側も楽しめる。ソレゾレが其々の立場で戦う。
男と女のLOVE。人間のLOVEが軸に描かれる。
(2019年6月29日掲載 2021年9月9日修正)
「YUME53 ― 劇団由さよなら公演 ―」
由最後の作品として、江口が提出したモノは、芝居人を主人公としたモノだった。
そして、"欲望という名電車"(テネシー・ウイリアムズ作)のブランチ的女を落ちぶれた女優に、スタンレーらしき男をモノを書かないシェークスピアマニア(かぶれ)の作家に設定している。
ソノ夢を見続ける姿を"花咲くチェリー"に投影し、しかも、夢を夢で終わらせぬ結末を用意している。
ブランチも原作では病院送りに成るのだが、ソノ再生を願って居る。
幾重にも施された構造に、江口のテーマでも在る親子(母と子)や、天使、ホームレス等が配されて彩りと物語の多様性と深さにも貢献している。トータルで"甦り"の物語なのかもしれない。
江口に影響を与えた大作家、テネシー・ウイリアムズとシェイクスピアへのオマージュ作ともいえる。
( 2019年6月12日 掲載 )
「風穴 ─1999激!“新撰組”A少年はバットで斬った─」
過去、現在、未来と描いている。
新撰組の話を軸に、大きな壁に風穴を開けようとした、負け組にフォーカスした作品。
彼等の信念から発する活力や、迷い葛藤。
桂小五郎が鞍馬天狗だったという斬新な新説を創り出し、悲劇の中でも楽しめる設えを施している。
その過去の新選組。
現在は、上演当時話題となった“バット殺人事件”にフォーカス。
少年が父親をバットで殺したというセンセーショナルな事件に思いを馳せ構築。
そして未来は 温暖化を通り越し氷河期?に入った日本、地球が舞台で、その一家族の楽しく?生きようとする姿、尚も、その家族の命も危うい姿を描き明るく?警告している。
その過去・未来・現在が絡み合いつぐまれる世界だ。
日本沈没やノストラダムスの予言等 世紀末を意識して、尚、人間の力を考える作品。
1982年上演作品。
上演時間を考えて創る江口作品にしては珍しく、ソレを無視してまでも入れたいモノを入れ込んでいる。
( 2019年6月12日 掲載 )
「愛の彷哮都市」
江口が唐十郎の紅テントを観たコトから生まれた作品。
由らしい美しい世界と、テントっぽい言い回し。
昔の人には懐しく、若い人には新鮮な世界のはず。
遊郭と娼婦宿の2軒の女を軸に、男女の愛、姉妹の愛。
老刑事と若い刑事のバディ愛。色々な謎が絡み合う。
絢爛な衣装や装置。役者の力量も試されるが、ソレが又、楽しい。
( 2019年4月28日 掲載 )























